徳島の空の玄関口
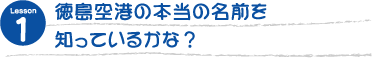
徳島空港の正式な名称は「徳島飛行場」と言います。徳島市の北約10kmの板野郡松茂町にあり、民間航空会社と海上自衛隊が共同で使っている全国的にも珍しい飛行場なのです。「徳島飛行場」は当初、昭和32年に防衛庁によって、海上自衛隊徳島航空隊基地として建設されました。その後、民間での利用を促す声が高まり、昭和37年に民間航空会社も利用する共用飛行場となったのです。

 徳島の空の玄関口、徳島空港ターミナルビル
徳島の空の玄関口、徳島空港ターミナルビル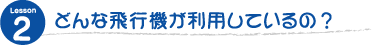
民間航空会社2社(JAL(日本航空)、ANA(全日空))と海上自衛隊が利用しています。現在、民間航空会社は東京、福岡、香港(季節便)を結んでいます。また、海上自衛隊の練習機や防災ヘリコプター、県警ヘリコプターも常駐し、利用しています。

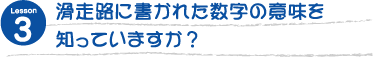
滑走路の末端に2桁の数字が書かれているのを知っていますか?徳島飛行場では海側に29の数字が入っています。飛行機では、方角を示す時、真北を360として、時計回りに方角を数字で表します。南西や北北西などと言うより、細かく表現でき、分かりやすいからです。そして、この3桁の数字の上2桁を取って付けているのが滑走路末端に付された数字なのです。さて、徳島飛行場の滑走路はどの方角に延びているのか、分かりますか?
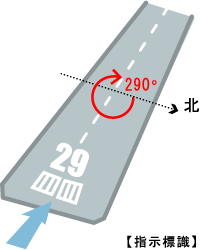
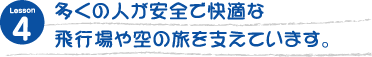
飛行機に関わる仕事と聞いて、ピンとくるのは、パイロットに客室乗務員、管制官などでしょうか。しかし、飛行機や空港はそれらの人々だけでは機能しません。飛行機の整備や給油、消防、出発カウンターで案内を行う旅客ハンドリング、搭乗口でのチェックを行うセキュリティーチェック、警備、施設案内などを行うインフォメーションセンター、手荷物検査などを行う手荷物ハンドリング、ショップやレストラン、清掃などの各セクションで働く人々が、旅客の皆さんの安全で快適な空の旅を支えているのです。

 次のフライトに向けての給油作業
次のフライトに向けての給油作業