地震に強いみなとのカタチ
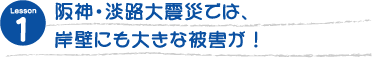
淡路島北端付近で発生したマグニチュード7.3の大地震は、死者・行方不明者6436人に及ぶ阪神・淡路大震災を引き起こしました。この大地震によって、都市圏などの陸上はもちろん、神戸港などの港も、岸壁が使用不可能になったり、岸壁背後の埋め立て地の液状化による建物の崩壊など大きな被害を被ったのです。その中で、地震に強い耐震構造の岸壁が軽微な被害で済んだことは、南海トラフ等迫る巨大地震に備えるための今後の港づくりに生かされなければならないでしょう。

 崩壊し、水没した岸壁
崩壊し、水没した岸壁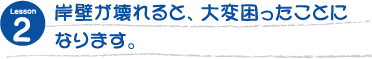
港湾は、海上交通と陸上交通の接点として、大切な役割を果たしています。しかし、岸壁が壊れると、貨物船やフェリー等の船舶が接岸できなくなり、人やモノの行き来が難しくなるのです。私たちの暮らしを支えている物資の出入りが途絶えてしまうと、県全体の経済にも大きな影響を及ぼし、私たち一人ひとりの暮らしにも少なからず支障をきたす可能性があるのです。

 大地震にも耐えた耐震強化岸壁
大地震にも耐えた耐震強化岸壁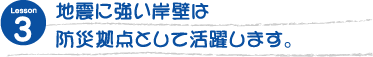
万が一、巨大地震が発生した場合、船舶による緊急物資の受け入れや、また避難者の輸送を円滑に大量に行えるのが港湾です。また、逆に他の地域で被害が発生している場合にも、援助物資を届けたり、またそれらを保管しておく基地としての役割を担うことができるのです。そのためにも地震に強く壊れにくい岸壁「耐震強化岸壁」が必要なのです。
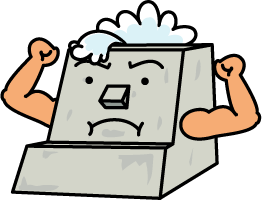
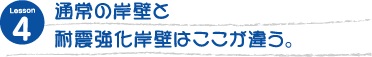
県内の企業、とくに製造業にかかわる会社が活動するために必要な材料が海外からやってきます。とくに林産品の輸入は輸入品目全体の約90%を占めています。また逆に、昔から、木材の積み出し港として産業の発展に役立ってきた徳島の港は、これからも地域の発展の拠点として、さまざまな役割りを果たしていきます。
通常の岸壁は、75年に1回程度の地震を想定して設計されています。一方、耐震強化岸壁は、近年発生が予測されている南海地震等の大規模地震を想定して作られます。同時に、岸壁の背後についても、地震による液状化を防ぐために、地盤を強固にします。
※現在の徳島県の耐震強化岸壁は次のようになっています。
徳島小松島港 沖洲地区 -7.5m岸壁(整備済)
沖洲地区 -8.5m岸壁(整備済)
赤石地区 -7.5m岸壁(整備済)
沖洲地区 -8.5m岸壁(整備済)
赤石地区 -7.5m岸壁(整備済)
橘 港 大潟地区 -5.5m岸壁(整備済)
浅川港 浅川地区物揚場-4m岸壁(整備済)
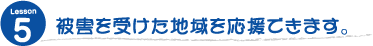
港湾は、物流拠点として地域の経済、あるいはもっと広い範囲での経済や産業の維持・発展に役立っています。仮に地域が被害を受けた場合にも、港湾が十分に機能していることで、海上輸送による人やモノの円滑な移動を支え、被災後の復興がより早く進むはずです。

 大地震発生後、有力な緊急的交通手段となった海上輸送
大地震発生後、有力な緊急的交通手段となった海上輸送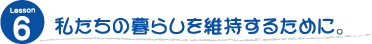
大地震によって、たとえば被災地を通過する陸上交通が被害を受けた場合、人やモノの移動が難しくなります。そうしたとき、海上から大量の人やモノを運ぶことができる船舶は、バイパスの役割を果たすことができます。また被害を受けた港湾からの輸送を代わって行うことも可能です。そのためにも、耐震強化岸壁を作り、海と陸との接点を確保しておくことが大切なことなのです。

 コンテナバースでの荷役作業
コンテナバースでの荷役作業
被災後に避難できる場所として、港の背後には防災拠点緑地の整備等も行っています。たとえば徳島小松島港赤石地区にある水深7.5mの耐震強化岸壁背後の和田島緑地には、耐震貯水槽を備えており、日頃は多目的広場として利用されています。また、このスペースは、仮設住宅建設地としても利用できます。

 和田島緑地の多目的広場
和田島緑地の多目的広場
